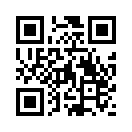2012年01月01日
◆2012年 『古事記編纂1300年記念』

◆2012年 『古事記編纂1300年記念』
今年2012年は、日本最古の歴史書である『古事記(こじき・ふるごとふみ)』が編纂されて1300年を迎えます。この古事記という書物には「国土の誕生について」「日本の神々について」「日本の歴史について」、「日本」と「日本人」のこの国のすべてのことが古代の人々の感性で語られています。
また、日本全国の神社で祀られてる「アマテラス」「スサノヲ」「オオクヌシ」などの神々の物語である「天の岩屋戸開き」「八岐大蛇退治」「稲葉の素兎」などがいきいきと描かれています。
『古事記』は、「日本」と「日本人」のことを考えるとき、一度は読んでほしい深い価値のある書物であり、それだけでなく大変に面白い書物です。この記念すべき年を機会に、ぜひ読んでみてください。
◆スサノヲ・ブログ -古事記編纂1300年記念-
http://www.susanowo.com/
◆日本の神話と古代史と文化《スサノヲの日本学》
http://susanowo.shiga-saku.net/
◆地域を幸せにするWebプロデューサー/神社魅力プロデューサー
http://www.ustream.tv/recorded/19336205
2012年01月01日
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(一)

◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(一)
日本の年中行事の中で古来よりの祭りの色彩を最もよく残しているのが正月と盆である(日本人にとっては一年の大きな節目として冬至と夏至の二度あった)(※注1)。
かつては数え年で、正月(※注2)になると日本人はみな一つ歳を取った。また、正月には万物万霊(森羅万象)の魂が新しく生まれ変わるとされた。
それだけに正月の行事は種類も多く、心構えの上からも一年のうちで最も重視されてきたのである。(※注3)。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1) 「盆と正月が一緒にきたような」といわれるように、正月と盆はハレの行事の二つの代表になっていて、いつも対比してみられてきた。
正月と盆とは不思議な対応と類似がみられる(年棚と精霊棚、門松と盆花とり、トンド焼きと迎え火・送り火、七日正月と七日盆など)。一年をきっちりと折半した形で、正月と盆とは半年を間において向かい合っているのである。
盆が七月の十四日・十五日を中心にしているのに対して、正月も十四日・十五日は小正月とか望正月といっていろいろの重要な行事がここに集中してみられる。ちょうど半年を間にした満月の夜に盆も正月も盛んな行事があるのである。
また正月朔日から大正月が始まるのに対して、盆のほうも七月一日を釜蓋朔日といって、地獄の釜の蓋が開いて、精霊たちがこの世に旅立ちをする日だといわれるし、この日に盆の路作りを始める地方もあり、盆も一日から始まるのである。
ただこの二つを同質同性格のものとするにはなお問題が残る。正月は季節の転換の祭り、農耕予祝の祭り、さらに祖霊の祭りといった総合的な性格を持っているのに対して、盆は祖霊・精霊の祭りが中心で性格は正月に比べ単純である。
(※注2) 正月は元々、年の初めにあって歳神の来臨を仰ぎ、その年の五穀豊穣を祈る、地域ぐるみの祭りであった。このために歳神の依り代として門松を立て、また不浄なものの侵入を防ぐために注連縄を張る。
さらに古風には、歳神を祀る年棚に御神酒や重ね餅を供えて灯明を点る。他方で、正月は祖先の霊が帰ってくる日でもあるので、この祖先の霊を迎えて祀る日とも考えられている。すなわち祖霊は年に二回、正月と盆に帰ってくるものとされていたのである。
しかし盆の方が仏教と強く結び付いたのに対して、正月の方は神道と結び付いたが、その神道も中世以降死の穢れのない清らかな祭りを強調するようになっていったため、正月が持つ祖先祭り(祖霊祭り、御魂祭り)の性格は極めて希薄なものとなっていった(西日本で今も残っている墓参り的風習は、その名残のようである。
(※注3) 日本人の「祖先崇拝」の中で、古代から最も重視されているのが「御魂祭り(祖霊祭り)」、すなわち「ご先祖様の祭り」である。
正月と七月の年二回、古くから収穫後の収納を完了した段階で祖霊を迎え、正月は米の、七月は麦の大規模な祭りを行っていた。
仏教伝来後、日本に伝統的にあった七月の御魂祭りは、仏教の「ウラバンナ(盂蘭盆)」と一緒になって、今日の盆になる。 正月行事も本来は、鏡餅に象徴されるように穀霊の祭りであるとともに、祖霊に供物を供える祭りであったのである。
また、春秋の彼岸も、本来は日本固有の祖霊祭りであった。日本人は、春秋二回の昼夜の長さが同じこの日、古くから御魂祭りを行っていた。
この春秋の御魂祭りには、祖霊のいる「常世の国」から、子孫がいる「この世」へ、祖霊が訪れると考えられていたのである。 仏教が伝来後の日本人の他界観は、海上の彼方の「常世の国」から、やがて阿弥陀如来のおわす「西方浄土」へと変わって行く。
このように日本人の古代聖俗観(宗教観、日本人の基層の世界観)とは、大自然とともに生き、その大自然に抱かれた魂の循環と再生のシステムへの素朴な信仰であることがわかる。
スサノヲ(スサノオ)
◆地域を幸せにするWebプロデューサー/神社魅力プロデューサー
http://www.ustream.tv/recorded/19336205
2012年01月01日
◆正月の起源と生命の循環と再生のシステム

◆正月の起源と生命の循環と再生のシステム
※正月の起源については(大自然に抱かれた、魂の循環と再生のシステム)
太古の昔、古代の日本人(倭人)には倭人の時間観(暦)があったようで、その時間観(暦)は太陽と月が規定していたようである。では、その倭人の時間観(暦)とはどういうものであったのであろうか。
それは、世界と人間が「死と再生」を繰り返す時間と考えていたようだ。時間とともに世界と人間は、死に再生するものだと考えていたと思われる。
倭人にとっては、中国の文明文化を受け入れた古代以前の太古において、時間観(暦)は、天空にある太陽と月であったはず。この二つの天体・太陽と月が太古の時間を基本的に規定し、年と月の観念が出来上がったと思われる。
年は太陽の周期で、その活動には二極の節目あった。すなわち最盛期と最弱期で、今で言う夏至と冬至の頃がそれにあたる。
そして冬至期こそが、太古の「正月」であったのかもしれない。正月とは一年の始まりである。始まるためには一度終わっていなければならない。すなわち死んでいなければならないわけである。
事実、世界の神話や祭祀を見れば、冬至は太陽の死である。そして同時に新たな太陽の誕生の時でもあった(太陽祭祀や太陽復活祭などから)。
もしかすると、太陽の死と再生のときが「正月」であったのかもしれない。それは太陽ばかりではなく、人間にとっても同じで、人間もこのとき死に、再び生まれ、蘇るのものと考えていたようだ。(夏至期の時にも、世界と人間は死と再生をくり返すと考えられていたようである)
月についても太陽のように、死と再生をくり返す。そして月の霊威の最盛期は満月の夜である。この夜、世界と人間は最大の生命エネルギー(生命力)を浴びる。これが「月見」だといわれている。
このように太古の時間観(暦)は、月の「死と再生~満月~死と再生」というひと月のリズムと、太陽の「死と再生~最盛期~死と再生」という一年のリズムとから成り立っていたようだ。そしてそのそれぞれの節目が「祭り」であり、ハレの日と夜であった。
この太古の時間観(暦)は、日本人の精神の深層(古層)にしっかりとあり、その後の中国文化(中国仏教も)の受容により春節(正月)などを取り入れ、古代国家による官製化がなされ、さらには欧米文化を受容してきたいま現在に至っても基本的には変わらなかったようである。
新文化を表層において、あるいはより深く受け入れても精神の基底においては「日本(太古の日本人の精神)」があったのである。
すると、死と再生こそが「正月」(祭り、ハレの代表)の本義であったことになる。このときに生命を更新しなければ、世界と人間はケガレ(気涸れ)てしまうのである。
よみがえり(黄泉返り)とは、文字どおり死んで再生することである。当然のことながら、本当に死んでしまったらよみがえれないので、象徴的に儀式的に死ぬことになる。
太古の時間観(暦)と農耕文化が確立してくると、再生の中心は稲霊(魂)に移り、またこれと並行して祖霊崇拝を軸とした魂祭りの要素が大きくなる。
時期的には、農作物の取り入れが終わり次の農作業が始まるまでの農閑期が、一年の中で集中的なハレの期間となる。こうして正月が年中行事の中でも揺るがぬ首座につくようになったようなのだ。
スサノヲ(スサノオ)
地域を幸せにするWebプロデューサー/神社魅力プロデューサー
http://www.ustream.tv/recorded/19336205